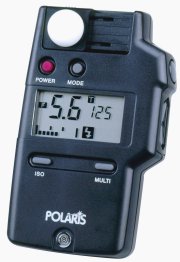オートバイ旅行では、雨が降れば、荷物が雨ざらしとなります。直射日光の下では、バッグの中はかなりの高温になりますから、カメラにとっては、非常にハードな環境となります。また、クルマのようにトランクに鍵がかかりませんから、盗難にも気をつかわなければなりません。
もちろん、そのための対策はするべきですが、限度があります。あまり高級なカメラを持って行って、神経質になっていると、肝心の旅行が楽しくなくなります。
私は、オートバイ旅行には、中国製の一眼レフ(ボディのみ9000円で購入)と、28mm、50mm、100mm、200mmという単焦点のレンズ4本を持って行きます。ボディはTEXERというブランドのもので、ミノルタのX-370と同じ製品です。このくらいの値段なら、たとえ壊れても、それほど惜しくありません。
「そんな安物のボディで大丈夫なのか?」と思われる方もいらっしゃるでしょうが、シャッターさえ、ちゃんと切れれば、ボディの機能としては十分です。
28mm以下の広角と、200mm以上の望遠は、あまり使用頻度が高くありませんから、持っていかなくてもいいと思います。28~200mmのズームレンズ1本、という選択もありだと思います。私はズームレンズがあまり好きになれないので、いまだに単焦点レンズを4本、持っていきます。

私がオートバイ旅行で持って行くカメラとレンズ

100円ショップで買ったプラスチックのケースに入れて、タンクバッグの中にセットしたところ
(緩衝材および断熱材として、やはり100円ショップで買った、ノートパソコンを入れるウレタンバッグを切って、内側に貼り付けています。つまり製作費は200円です。)